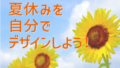数ある受験の中でも最も規模の大きいものが大学受験です。日頃生活する中ではあまり意識することのない大学受験のスケールの大きさを知って、目標や道筋を明確にしましょう。
ライバルは全国の精鋭 ~受験環境の違い~
高校受験と大学受験は、受験環境や条件から大きな違いがあります。
令和4年度の学校基本調査(文部科学省)によると、高校進学率は97%を越えており、ほぼ全員が高校に進学しています。一方で、四年制大学の進学率は、18歳人口の減少と反比例するかのように年々上昇を続けていますが、およそ2人に1人の割合(56.6%※)でしかありません。
※2021年度より1.7ポイント上昇。過去最高。
高校と大学の進学率の違いは、高校の学科の特性や高校で身につけた専門知識を生かしたいなどの理由から、就職や専門学校を選択することが影響しています。四年制大学への進学を希望する場合、高校受験の段階から大学入試を見据え、普通科(進学校)に入学・在籍するのが一般的です。入学後は、自分と同程度の学力と目標を持つ生徒が集まるため、「中学校のときは、こんな順位じゃなかったのに・・・」と、中学校と高校のギャップに戸惑う生徒も少なくありません。
続いて、大学入試に目を移してみると、18歳人口の減少により大学志願者は減少傾向にありますが、大学の受け皿は拡大しており、大学志願者と大学入学定員は、ほぼ同数です。まさに、大学を選ばなければ誰もが大学に入学できる「大学全入時代」は、目前に迫っています。その一方で、大学の二極化が進んでおり、受験生から人気のある国公立大学や一定の学力を要する難関私立大学では、依然として高い競争倍率が維持され、高い学力が必要とされています。これらの大学・学部を志望する場合は、高校入試よりも、はるかに厳しい競争を勝ち抜かなければなりません。
次に、令和4年度に四国4県の国立総合大学へ入学した学生の出身地を紹介します。
| 愛媛大学 | 香川大学 | 徳島大学 | 高知大学 |
| 愛媛県 757人 広島県 312人 岡山県 121人 香川県 95人 兵庫県 89人 | 香川県 371人 岡山県 297人 兵庫県 111人 愛媛県 84人 徳島県 65人 | 徳島県 403人 兵庫県 258人 大阪府 109人 岡山県 77人 愛媛県 63人 | 高知県 270人 愛媛県 85人 徳島県 66人 香川県 42人 近畿 198人 |
地元出身の学生が多いものの、一定の学生が地域をまたいで進学していることが分かります。大学受験は公立高校受験とは異なり、どの地域の大学でも受験できます。異なる地域、異なる当たり前の中で高校生活を送ってきたライバルたちとの真っ向勝負は、年間通して行われる全国模試を経て受験本番まで続きます。
高校受験と大学受験の倍率
高校受験と大学受験は倍率の点でも大きな違いがあります。また、高校受験の倍率も、地域によって異なります。
まず、四国4県の令和5年度公立高校受験の平均志願倍率を示します(定員÷志願者)。
愛媛県 0.89倍 香川県 1.15倍 徳島県 1.00倍 高知県 0.70倍
これらは全体の平均値なので、高校や学科によって差はあります。また、普通科でも高校ごとにばらつきがある県もあれば、おおむね1.0倍前後で横並びとなる県もあります。高校受験に強い危機感を持たないまま進学すると、「次も何とかなるだろう」という油断が生じやすくなります。しかし、大学受験では熾烈な競争を勝ち抜いた私立高校・中高一貫校の生徒も同じ土俵で戦いますので、自分の周囲の雰囲気だけで受験に対する姿勢を判断するのは危険です。
一方、令和5年度入学試験における、四国4県の国立総合大学前期日程の受験倍率が以下の通りです。
| 愛媛大学 | 受験倍率 | 香川大学 | 受験倍率 |
| 法文学部 教育学部 社会共創学部 理学部 医学部 工学部 農学部 | 1.6 1.3 2.0 1.6 2.7 1.5 1.6 | 教育学部 法学部 経済学部 医学部 創造工学部 農学部 | 1.6 1.3 2.0 1.6 2.7 1.5 |
| 徳島大学 | 受験倍率 | 高知大学 | 受験倍率 |
| 総合科学部 医学部 歯学部 薬学部 理工学部 生物資源産業学部 | 1.0 2.1 4.7 4.0 1.6 2.1 | 人文社会学部 教育学部 理工学部 医学部 農林海洋科学部 地域協働学部 | 1.6 1.3 1.7 2.6 1.8 1.1 |
section1でも述べたように、大学受験を希望するのは18歳人口のうち6割程度。その人たちが全力で勉強をした先にこれらの倍率はあります。国公立大学を初めから志望しない人もいる中、2.0倍を大きく超えるところもあり、狭き門であることが分かります。
受験生としてどう過ごすべきか
ここまで、受験環境や倍率の観点で大学受験の大変さをお伝えしてきました。section2で述べたように、様々な受験体験を高校入学までに重ねてきたライバルたちが、大学受験では同じ土俵で戦います。とは言え、全国のライバルの学習状況や生活を間近で観察するのは難しいです。すると、時に油断や中だるみが起こることもあります。受験当日にベストな自分で臨むために、自分がどれくらい成長できたかにフォーカスしなければいけません。だから、受験とは「自分との戦い」とよく言われます。
自分が置かれた環境でどう最善を尽くすか、今の自分の状態の良し悪しをどう判断するか。これらは全国模試の結果から数値で測ることもできます。しかし、それだけでは不十分です。周りにいる、学校の先生や塾の先生に相談してみましょう。すると、過去の受験生の様子をもとに、客観的な意見や改善策を聞くことができるでしょう。受験に向けては圧倒的な努力が必要です。それに加えて、努力の方向性が正しいかどうか、自分の状態を常に点検する習慣を持つことが大切です。